この記事では、私が夫に熟年離婚を突然切り出された原因について、自分なりに考えたことをご紹介します。
正直なところ、本当の理由は夫に確認していないため、「多分、こうだったのかな?」という推測になります(-_-;)
また、一般的な熟年離婚の原因や傾向についても合わせてお伝えします。
夫に熟年離婚を切り出された状況
私の場合、子供の就職を機に夫から熟年離婚を切り出されました。
- 夫婦ともに50代前半
- 婚姻期間は25年以上
- 夫100%名義の戸建て住宅所有(残債あり)
- こども2人(ともに社会人)
- 夫婦ともにフルタイムの正社員
- 妻の婚姻期間中の扶養期間16年
その時の心境はこちらにも書いています↓

夫から離婚を切り出された直後は冷静に受け止めることができず、何が起こっているのか分かりませんでした。
その日の夜から、悶々と「どうしてこんなことになったのか」「何かいけなかったのか」と考える日が続きました。
最近の熟年離婚の傾向と主な原因

最近の熟年離婚の傾向
最近、熟年離婚は増加傾向にあります。特にこの5年間で2倍以上に増加しているとも言われており、コロナによる生活環境の変化も影響しているようです。
以前は熟年離婚といえば妻から夫に離婚を切り出すケースが圧倒的に多かったのですが、現在では夫から妻に離婚を切り出す割合も約4割に増えています。
「10年ほど前までは女性が離婚を求めるケースが8割でしたが、現在は男性から切り出すケースが4割に急増しています。夫たちが“この妻と20年近い老後人生を共に歩めるか”を考えて離婚を決断するようになっているのです」
男女別の熟年離婚原因
熟年離婚の原因としてか男性と女性では異なる要因があるようです。
- コミュニケーション不足
- 経済的な問題
- セックスレス問題
- 個人の趣味や目標の実現
- 家庭内業務の不均衡
- 感情の不一致
- 子育ての終了に伴う今後の夫との関係性
- 働き方の変化などに伴う優先順位の変化
- 不倫や浮気
- 健康や介護の問題
いずれの理由も男女を問わず、多くの人が抱えている問題かもしれません。

私が夫に離婚を切り出された原因
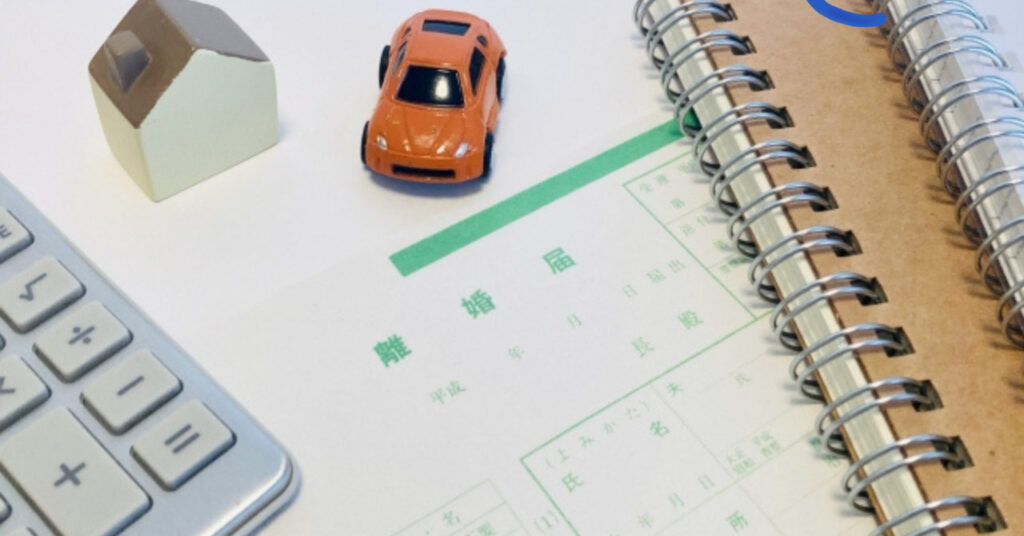
私自身の状況を、一般的な熟年離婚の原因に当てはめて考えてみました。
コミュニケーション不足
夫は長年単身赴任をしており、家族の中での存在感が薄れていました。私と子供の関係は深まる一方で、夫は家族の中で疎外感を感じていたのかもしれません。

とはいえ、自分の方から積極的に関わってくることもなかったので受け身で捉えられても…と思わなくはないです。
経済的な問題
私は数年前に正社員として働き始め、その後の転職を経て経済的にも自立した状態です。
ですが、数年前までは夫の扶養に入っていたため、主たる稼ぎは夫で子供の学費や家のローンなど、すべて夫に依存していました。
経済的に妻が自立した今、自分が妻を養わなければならない義理もないし、そもそも自分の稼ぎがこれまで全て消えていったことも不満だった、というところでしょうか?
これからは「自分で稼いだお金は自分で好きなように使いたい」と思っていたかもしれませんね。
セックスレス問題
レスになってから10年以上経ちます。すでに男女の愛情というものはなくなっていたと思いますが、一度キッカケを失うと改めて再開することもできないので、こちらもそれなりに不満はあったかもしれません。これはお互い様ですけどね。


個人の趣味や目標の実現
夫と私は趣味や価値観が異なり、一緒に楽しむことがありませんでした。そのため、「このまま一緒にいるよりも、自分の時間を自由に使いたい」と思ったのかもしれません。
家庭内業務の不均衡
家事負担は私9割、夫1割。私にとっては大きな不満でしたが、夫には不満はなかったと思います(笑)。
熟年離婚を切り出したのは結果的に夫だったけど
夫に離婚を切り出されたことで「サレ側」ではありますが、実際には私も離婚を考えていました。
- 家事の負担に対する不満
- 夫との関係性の希薄さ
- 子育て終了後の生活の変化
離婚を切り出されたこと自体はショックでしたが、今となっては「無事に離婚できたこと」に感謝すら感じています。
夫に熟年離婚を切り出された原因まとめ
一般的な熟年離婚の原因と比較すると、私のケースも特別なものではなく、ごく普通の熟年離婚でした。
若い頃なら「性格の不一致」が離婚理由になることが多いですが、20年以上連れ添った後では「性格が合わない」では済まない事情が絡んできます。
経済的な問題も離婚の大きなハードルになりますが、無事に離婚できたことを前向きに捉えています。
夫に離婚を切り出された直後は「どうしてこんなことに…」と悩みましたが、振り返ってみると熟年離婚の典型的なパターンだったと分かり、少し気が楽になりました。
もし同じように悩んでいる方がいたら、自分の状況と照らし合わせて、少しでも安心材料にしていただければと思います。
