熟年離婚を決意したとき、まず大切なのはお互いに納得できる形で話し合いを進めることです。そのために欠かせないのが「離婚協議書」。これは、離婚の際に決めた内容を文書として残しておくもので、後々のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
この記事では、離婚協議書の役割や作成のポイント、離婚協議書の基本的な内容をご紹介します。さらにテンプレート(サンプル)として私の離婚協議書をダウンロードできるようにご用意しました。

こんなものを公開することになるとは思いませんでしたけど・・・www
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が話し合って決めた離婚条件を記録した書類です。
これを作成することで、口約束だけでは曖昧になりがちな内容を明確にし、後のトラブルを防ぐことができます。特に、熟年離婚の場合は財産分与や年金分割など、将来の生活に関わる重要な決定が多く含まれるため、しっかりと作成しておくことが大切です。
また、公証役場で「公正証書」にしておくと、法的な効力が強まり、支払いの履行が確実になります。
離婚協議書を作成するために知っておくべきこと
離婚協議書に記載すべき内容
離婚協議書には、主に以下のような内容を記載します。
- 離婚の合意
-
夫婦双方が合意の上で離婚することを明記します
- 財産分与
-
共同で築いた財産の分配を明確に決めることは必須です。不動産や金融資産の分配について、詳細に記載することでトラブルを防げます。
-
また借金がある場合の負担方法についても明記します。
- 慰謝料の有無や金額
-
離婚の原因によっては、どちらかが慰謝料を支払う場合があります。慰謝料の有無や負債の分担についても、協議書に記載しておきましょう。
- 年金分割
-
熟年離婚の場合は特に重要です。近い将来受け取る年金について、分割の割合を明記します。
- 生活費や扶養義務(必要に応じて)
-
専業主婦(夫)だった場合、一定期間の生活費を支払う必要があれば明記します。
- 親権と養育費
-
未成年のお子さんがいる場合、親権や養育費の取り決めを明文化することが重要です。熟年離婚ではお子さんが成人しているケースも多くなります。その際には親権の取り決めは発生しません。
ただし、熟年離婚の場合は上記の内容以外にも以下の内容についても追記が必要となります。
- 退職金の扱い
-
将来もらう予定の退職金が財産分与の対象となる場合、合意した分与の割合を明記します。
- 持ち家の扱い(住宅ローン含む)
-
どちらかが引き続き住むのか、売却するのかによって記載すべき内容も異なります。
どちらかが住む場合、不動産の価値やローンの残額を考慮して分与する必要があります。
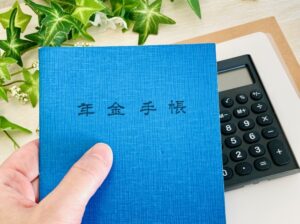
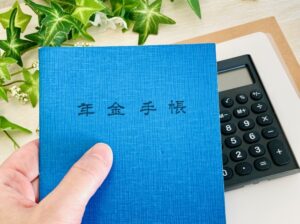
法的効力を持たせるためのポイント
離婚協議書自体のフォーマットは自由ですが、特に金銭的な約束(養育費や慰謝料など)を確実に守らせたい場合は公正証書化します。
公正証書として有効なものとするためには、以下のような一定の要件を満たす必要あります。
- 夫婦双方が自筆で署名。印刷された署名や捺印のみでは、法的に不十分となる場合があります。
- 甲(夫)・乙(妻)の氏名、住所を明記すること。
- 作成日を記載すること。
- 必要に応じて強制執行認諾条項(支払いが滞った場合に強制執行できる文言)を入れる。


離婚協議書のテンプレート活用方法
離婚協議書のテンプレートを活用するメリット
法的効力と明確性の確保
テンプレートには一般的な項目が含まれており、状況に応じて修正すれば法律的に有効な書類を簡単に作成することができます。
また、テンプレートを活用しながら話し合うことで決めるべき事項が明確になり、話し合いもスムーズに進みます。法律に基づいた書類を作成できるため、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
手間の削減と時間の節約
ゼロから作成する手間が省けるため、時間を大幅に節約できます。後に専門家に相談する予定がある場合も、事前ぞほテンプレートで整理しておくことで、弁護士や司法書士との相談がスムーズになります。
精神的な負担の軽減
決めるべきことが明確になっているため、ある程度感情的になることを防ぎ精神的な負担の軽減につながります。
コストの削減
基本的な部分を自分で作成することで弁護士に依頼する部分を最小限に抑えられます。
テンプレートを利用して離婚協議書を作成し、弁護士・行政書士を通さずに公正証書化することも可能です。ただし、公証人がチェックを行い、不備があれば修正を求められるため、必ずしもそのまま通るとは限らず、証書化するための手続きに時間を要する場合があります。
離婚協議書のテンプレート
以下は基本的な離婚協議書の内容です。
夫〇〇(以下「甲」という)と妻〇〇(以下「乙」という)は、協議のうえ、次のとおり離婚することに合意した。
第1条(離婚の合意)
甲と乙は協議離婚することに合意し、離婚届を〇年〇月〇日までに提出する。
第2条(財産分与)
- 甲は、以下の財産を乙に譲渡する。
- 銀行預金(〇〇銀行、口座番号XXXXXX)
- 自動車(車種:〇〇、ナンバー:〇〇〇)
- 乙は、以下の財産を甲に譲渡する。
- 不動産(所在地:〇〇)
第3条(慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として〇〇万円を〇年〇月〇日までに支払う。
第4条(年金分割)
甲の年金の〇%を乙に分割することに合意し、必要な手続きを行う。
第5条(その他)
本協議書に記載のない事項については、甲乙協議のうえ、円満に解決するものとする。
以上、協議が成立したことを証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ1通を保管する。
〇年〇月〇日
甲(署名・印)
乙(署名・印)
実際は本当にケースバイケースで色々なことを決めていかなければなりません。
参考までにかなりリアルな私の離婚協議書(案)をダウンロードできるようにしておきます。



ダウンロード版は本物の3分の2程度の内容です。実際はもっとボリュームがありますが、万人に当てはまる内容でもないので割愛しました
離婚協議書を作成するときのポイント
感情的にならず冷静に話し合う
離婚協議書は、将来の生活を左右する大切なものです。感情的にならず、冷静に話し合いましょう。
専門家に相談する
内容によっては、弁護士や行政書士に相談するのもおすすめです。特に財産分与や年金分割に関しては、専門家のアドバイスを受けると安心です。
できるだけ具体的に記載する
「あとで決める」ではなく、できるだけ細かく内容を決め、書面に残しましょう。
公正証書にする
公証役場で「公正証書」にしておくと、支払いが履行されない場合に強制執行が可能になります。
離婚協議書の重要性とテンプレートまとめ
熟年離婚では、財産分与や年金分割といった重要な決定事項が多く、離婚協議書を作成しておくことが将来のトラブル回避につながります。テンプレートを活用しながら、自分たちに合った協議書を作成し、納得のいく離婚を進めましょう。
また、迷ったときは専門家のアドバイスを受けることも大切です。新しい人生のスタートを、安心して迎えられるようにしましょう。
